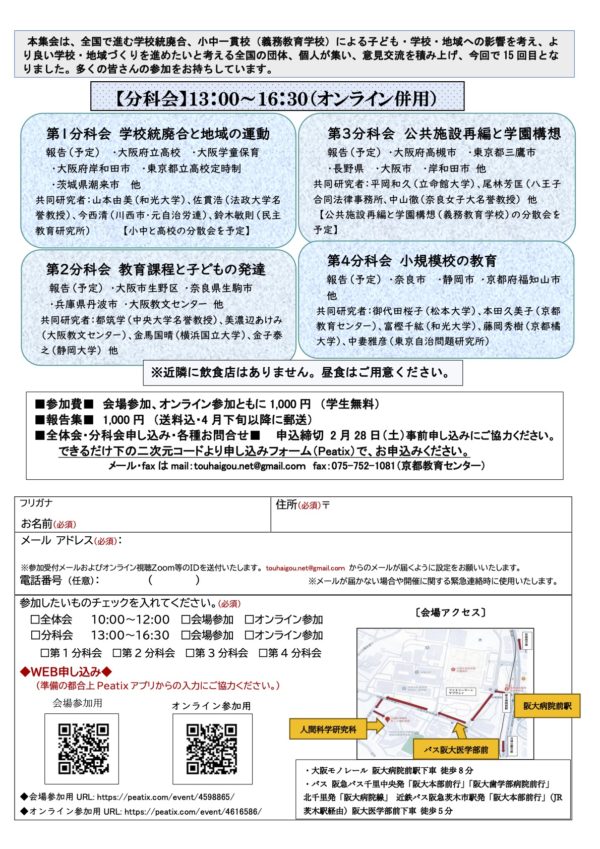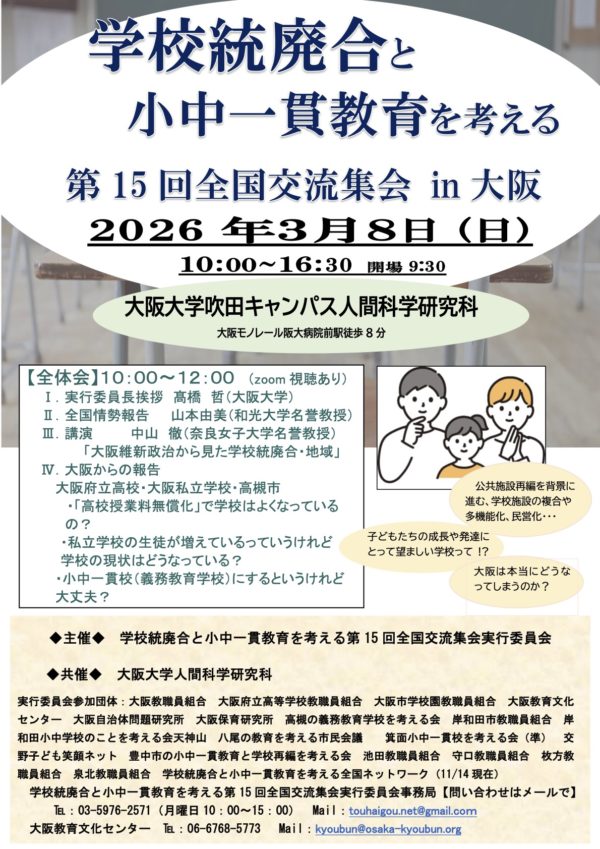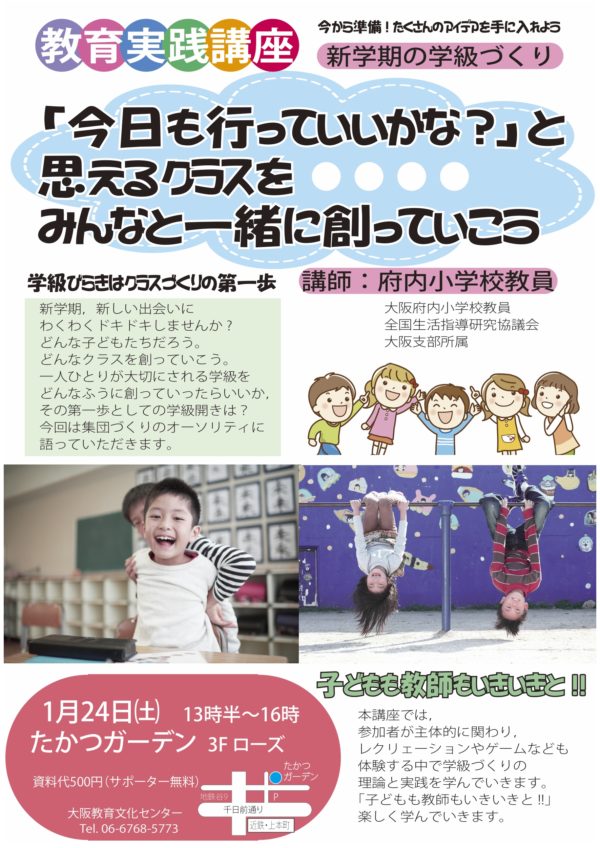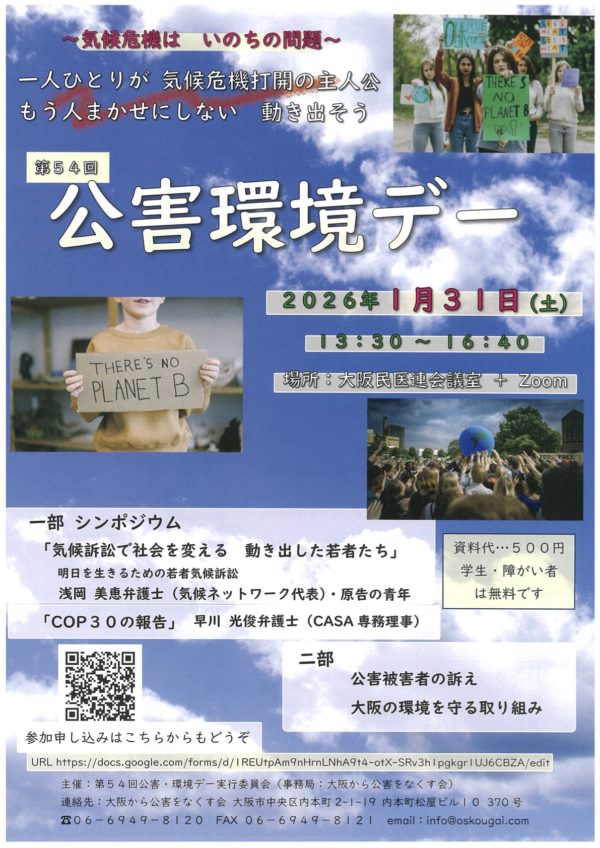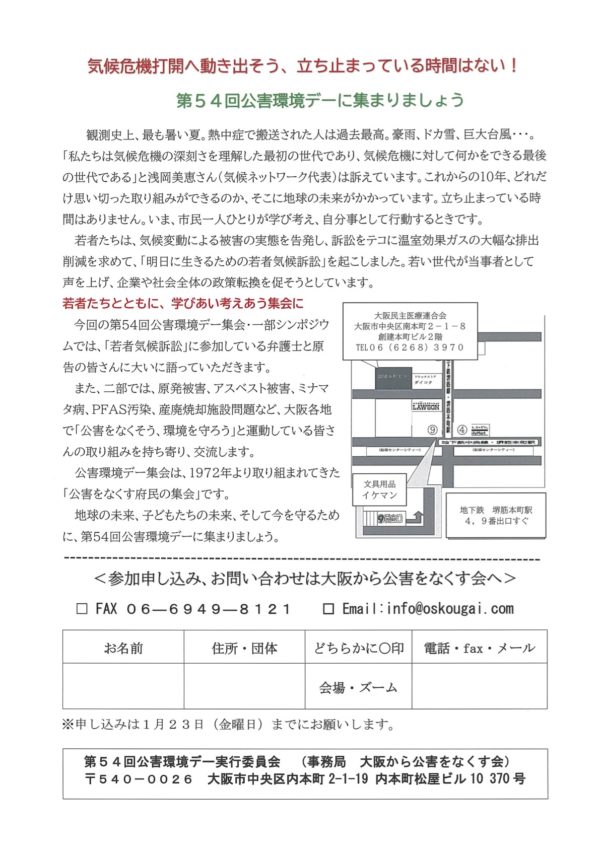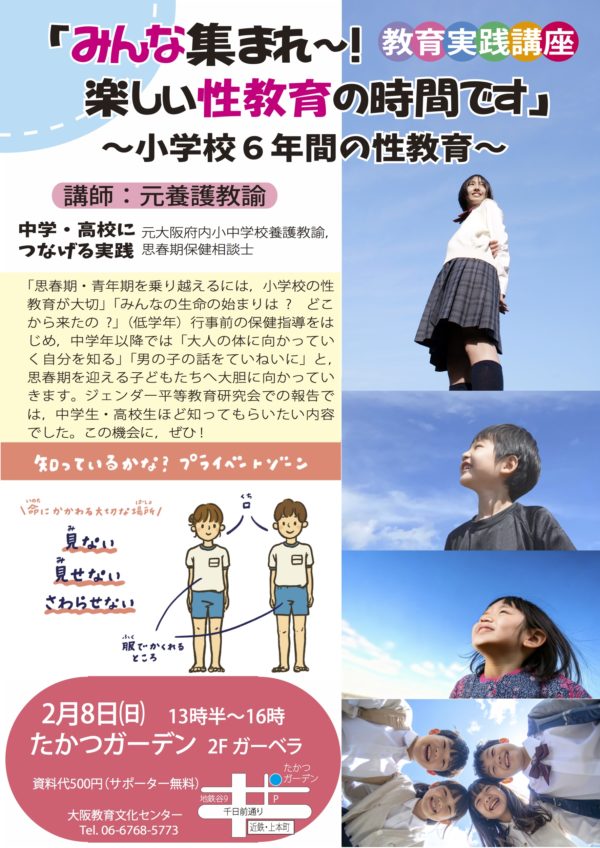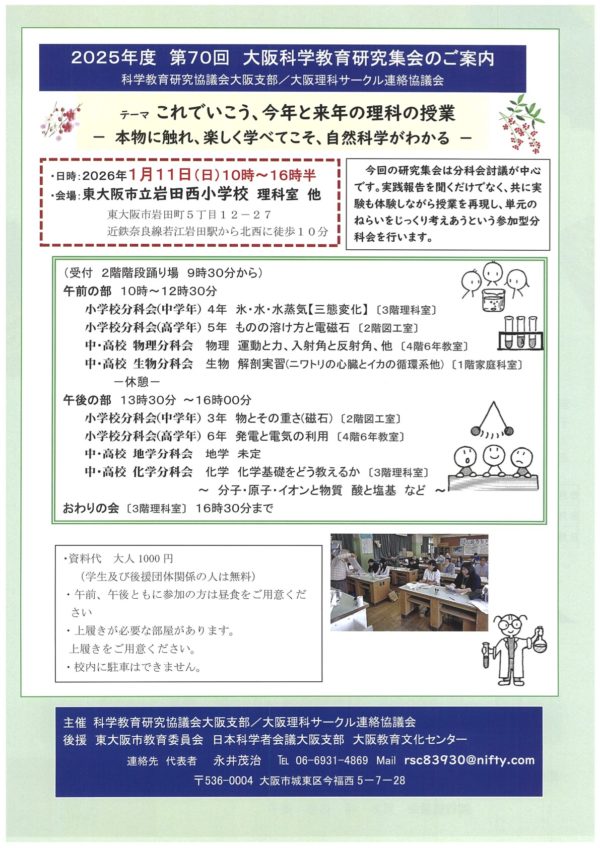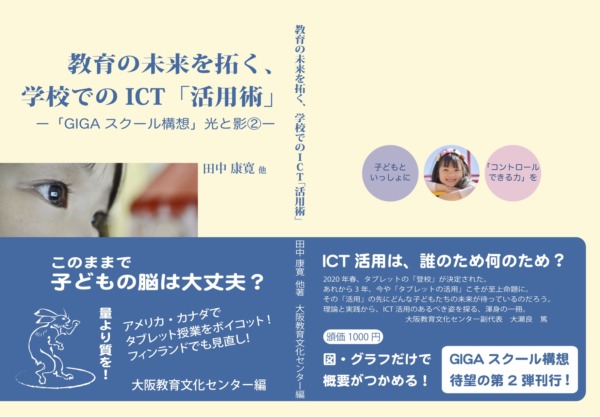学校統廃合小中一貫教育を考える
第15回全国交流集会 in 大阪
2026年3月8日(日)10:00〜16:30 開場9:30
大阪大学吹田キャンパス人間科学研究科
大阪モノレール 阪大病院前駅 徒歩8分
【全体会】10:00~12:00(zoom視聴あり)
I. 実行委員長挨拶 髙橋哲(大阪大学)
II. 全国情勢報告 山本由美(和光大学名誉教授)
III. 講演 中山徹(奈良女子大学名誉教授)
「大阪維新政治から見た学校統廃合・地域」
IV. 大阪からの報告
「高校授業料無償化」で学校はよくなっているの?
・私立学校の生徒が増えているっていうけれど
学校の現状はどうなっている?
・小中一貫校(義務教育学校)にするというけれど大丈夫?
◆主催◆
学校統廃合と小中一貫教育を考える第15回全国交流集会実行委員会
◆共催◆
大阪大学人間科学研究科