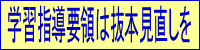 新学習指導要領 職場討議資料 > 音楽
新学習指導要領 職場討議資料 > 音楽
大阪教職員組合 「教育課程・教科書」検討委員会
音楽
目標について
他の教科等においても、「目標」で、「○○の見方・考え方」、「資質・能力」という変更がみられますが、音楽でも同様に、「目標」において、「音楽的な見方・考え方を働かせ」「音楽と豊かに関わる資質・能力を育成することを目指す」とされており、総則で強調されている「見方・考え方」「資質・能力」が音楽でも強調され、現行学習指導要領とは違う構造となっています。
そして、この目標は3点に細分化され、(1)曲の理解と表現の技能、(2)表現の工夫と鑑賞、(3)感性・態度、とされています。
現行の目標にあった「音楽活動の基礎的な能力を培い」という表現は消え、現行の「音楽を愛好する心情と音楽に対する感性」については、文言として残しているものの、それが、「音楽に親しむ態度」に収れんされています。改悪教育基本法第2条の教育の目標は、すべて「○○する態度」とされていますが、それが、音楽にも表れており、「態度主義」という改悪教育基本法の具体化が読み取れます。
各学年の目標及び内容について
「各学年の目標及び内容」については、低学年から難しいことを要求しているのが特徴です。たとえば、小学校1・2年生では、「曲想と音楽の構造などとの関わりについて気付くとともに、音楽表現を楽しむために必要な歌唱、器楽、音楽づくりの技能を身に付けるようにする」という目標が第1に置かれていますが、現行の「楽しく音楽にかかわり…生活を潤いのあるものにする」や「様々な音楽に親しむようにし、基礎的な鑑賞の能力を育て、音楽を味わって聴くようにする」などと比べても、大変高い目標と言わざるを得ません。また、音楽を楽しみ、音楽を生活に取り入れるという文化的な広がりではなく、理屈っぽい音楽になってしまうのではないかと危惧されます。
この高い目標は、「表現」にもあらわれています。現行学習指導要領では、1・2年生の歌唱では、「歌詞の表す情景や気持ちを想像したり、楽曲の気分を感じ取ったりし、思いをもって歌うこと」とされていますが、新学習指導要領では、「歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら、豊想を感じ取って表現を工夫し、どのように歌うかについて思いをもつこと」となっています。
この立場で子どもを指導すれば、音楽嫌いの子どもを大量に生み出すことにならないでしょうか。大変気になるところです。
このような、音楽から「楽しさ」を後景に追いやる傾向は、3・4年生においても同様です。現行学習指導要領では、3・4年生の目標は、「音楽活動への意欲を高め」「音楽表現の楽しさを感じ取るようにする」「様々な音楽に親しむように」などという文言が使用されていますが、新学習指導要領では「豊想と音楽の構造などとの関わりについて気付くとともに、表したい音楽表現をするために必要な歌唱、器楽、音楽づくりの技能を身に付ける」をはじめとした目標が掲げられていますが、そこには「表現する意欲」という文言は見当たりません。また、「音楽活動をする楽しさ」という文言はありますが、音楽そのものを楽しむという表現はなされていません。
5・6年生でも、現行の「音楽表現の喜びを味わう」という文言は消えてしまっています。
これをはじめとして、新学習指導要領には、「技能」、「身に付ける」という言葉が何度も繰り返し出てきます。また先に述べた「曲想と音楽の構造との関わり」をはじめとする「~との関わり」や、「音の特徴」「フレーズの特徴」などにも「気付くことができるよう指導する。」となっています。
さらに音楽づくりでは、「即興的に~表現する技能」という言葉が新たに加わっています。
指導計画の作成と内容の取扱いについて
「指導計画の作成と内容の取扱い」では、繰り返して「資質・能力」の育成が強調され、「主体的・対話的で深い学びの実現」という総則の文言が繰り返されています。これを見ても、総則ですべての教科、教科外の活動を縛るという新学習指導要領の重大な問題点を指摘することができます。
また、「君が代」の取り扱いについては、現行学習指導要領策定のときにも厳しい批判が寄せられた「いずれの学年においても歌えるよう指導すること」が新学習指導要領でも同じ文言で記されています。道徳が「特別の教科」とされることと併せてみたときに、今以上に押しつけが強められる危険性を感じざるを得ません。
私たちの対抗軸
週に1~2時間しかない音楽の学習は、「音楽を楽しむ」ことを大切にしてとりくみたいものです。新学習指導要領にあるような、曲の内容を理解したり演奏の技能を身に付けたりすることに重きを置くようなことになれば、本当に面白くない音楽の授業になってしまいかねません。
また、「理解」を評価するために、書いたり話したりする表現活動が増え、歌唱や演奏の時間が減ることも考えられます。
「音楽は難しい、つまらない」と感じる子どもや教師が増えないようにするには、私たちにとって、「音楽を楽しむ」「音楽に親しむ」ことを大切にした授業をすることは欠かせません。
音楽をはじめ、芸術においては、「表現意欲」「表現内容」「表現能力」のどれ一つ欠かしても楽しい授業にはなりません。「知識・技能」「資質・能力」偏重の音楽の授業ではなく、子どもたちのさまざまな表現や考えを広く受け止め、楽しい授業をつくっていくことをめざすことが大切です。
